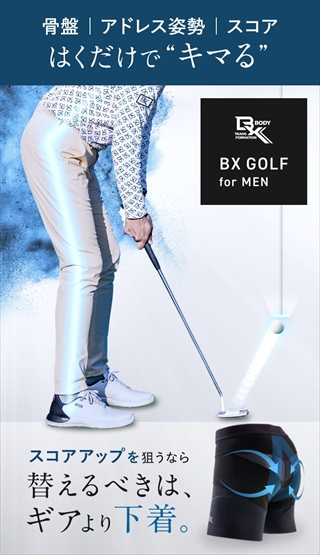<本サイトは記事内にPRが含まれています>
- 腰にこりしたものがあって心配これは一体何
- 腰のこりや張りの原因は
- 「腰のこりや張りをほぐすストレッチ」
「腰に触ってみたら、こりこりしたものがあって心配」
「これはいったい何?」
…そんなお悩みをお持ちではありませんでしょうか。
もしかしたら、そのこりこりは腰のコリや張りが原因かもしれません。
では、腰のコリや張りはなぜ起こるのでしょうか。
また、どこに腰のコリや張りは出やすいのでしょうか。
今回の記事ではコリや張りの原因、および腰をほぐすストレッチについてご紹介しています。
腰のこりこりが気になる方はぜひ、参考にしてみてくださいね。
「腰のこりこりしたもの」固まりは何?
腰のコリと張りをほぐすストレッチを紹介する前に、そもそもこりこりしたものの正体が何なのかを知っておきましょう。
こりこりが痛い場合と、痛くない場合とに分けてご紹介します。
腰のコリコリしたものが痛い場合
腰のこりこりしたものが痛い場合、次のような可能性が考えられます。
・腫瘍
腰のこりこりしたかたまりが痛い場合、腫瘍ができているのかもしれません。
腫瘍といっても驚かれる必要はありません。腫には「腫れる」、瘍には「できもの」といった意味があります。
つまり、腫瘍=ガンとは限らないのです。
ただし自己判断は危険なので、心配な場合は医療機関で見てもらいましょう。
・筋緊張
腰のこりこりしたかたまりを押した時に、「痛い」「気持ちいい」と感じる場合、筋緊張を起こしている可能性があります。
とくに筋筋膜性の腰痛を起こしている場合、特定の場所にしこりを認めるケースは珍しくありません。
人によってはゴリゴリと表現されるケースもあります。
腰のコリコリしたものが痛くない場合
腰にこりこりしたかたまりがあるものの、痛みがない場合には次のような可能性が考えられます。
・粉瘤(ふんりゅう)
粉瘤は皮下に小さな袋ができ、そこに角質や皮脂が溜まる皮膚疾患です。
通常痛みはありませんが、感染症を起こした場合、痛くなるケースもあります。
ニキビと勘違いされるケースもありますが、粉瘤は自然治癒しないため、皮膚科で見てもらう必要があります。
・脂肪腫
脂肪腫は、主に皮下組織へと脂肪がたまる疾患です。
中年期の女性に多く見られ、通常は痛みがありません。
5㎝以上になる場合、悪性腫瘍との鑑別をおこない、手術で取り除くケースもあります。
腰 のコリが起こる場所はどこ
腰のこりこりしたかたまりがある場合、多くの場合は筋肉の緊張が原因と考えられます。
コリが起こりやすい場所としては、次のようなポイントが挙げられます。
・おへその高さ
腰骨の左右、おへその高さにコリを起こすケースが少なくありません。
東洋医学的には「志室(ししつ)」と呼ばれるツボがあるポイントです。
腰が重だるいとき、自然と手で押さえている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
・骨盤の上
腰のコリは骨盤の上にもよく見られます。
解剖学的には腰方形筋(ようほうけいきん)と呼ばれる筋肉が付着する場所です。
ぎっくり腰を起こしたときに痛くなるケースも少なくありません。
・肋骨の下
骨盤と反対側の腰方形筋の付着部が、12番目の肋骨の下部です。
12番目(一番下)の肋骨の下から腰が始まるのですが、そこにこりこりしたかたまりができるケースも少なくありません。
腰こりのチェック方法は?
こりこりしたものが腰コリかどうかを判断する簡単な基準が、温めたり押したりして、楽になるかどうかです。
マッサージや入浴でこりが緩和するようであれば、腰コリと判断してよいでしょう。
腰のこりや張りの原因は
腰のコリや張りが起こる原因としては、主に次のような例が挙げられます。
腰のこりの原因①疲労
腰に限ったお話ではありませんが、筋肉が硬くなる原因は「使い過ぎ」と「不動」の2つです。
筋肉を使い過ぎて疲労した場合、腰のコリや張りが起こりやすくなります。
腰のこりの原因②長時間の同一姿勢
前述の通り、筋肉が硬くなる原因の1つとして、不動が挙げられていました。
デスクワーカーの方など、長時間の同一姿勢を強いられた場合、腰のコリや張りが出やすくなります。
腰のこりの原因③血行不良
全身の血行が悪くなると、疲労物質や老廃物が腰まわりに溜まりやすくなります。
その結果、腰のコリや張りが出やすくなります。
腰のこりの原因④不良姿勢
猫背や反り腰といった不良姿勢がある場合、腰にかかる負担が増大します。
そのような姿勢を続けると、腰のコリや張りが出やすくなります。
腰のこりの原因⑤睡眠不足
睡眠不足も腰のコリや張りがでる原因となります。
私たちの身体は睡眠中に回復しますが、睡眠不足に陥ると回復力が低下するからです。
また、寝返りを打ちづらい寝具も、腰のコリや張りを引き起こす原因となります。
腰こりと張りをとるストレッチ
腰のコリがなかなか取れない場合、「どうするとよいのか分からない」といった方もいらっしゃるでしょう。
実は、腰のコリや張りをとるには、ストレッチで筋肉をほぐすのが効果的です。
ただし、腰の痛みにまで進行してしまうと、ストレッチの効果が期待できないケースも少なくありません。
そのため、腰コリや張りの段階で対処するのが重要です。
日常的な腰の疲れを取る方法でもあるので、ストレッチのやり方を知っておいて損はありませんよ。
①腰~臀部のストレッチ
腰のコリや張りは、臀部(お尻)の筋緊張によってもたらされるケースが少なくありません。
そのため、腰と一緒に臀部も同時にストレッチするのがおすすめです。
・ポイント
上半身がお辞儀しないよう、身体全体を捻じるよう意識しましょう。
・手順
1.ヨガマットや床の上に長座の姿勢をとる
2.右ひざを曲げ、右足を左ひざの外側におく
3.左ひじで右ひざを押しながら、身体を右側に捻じる
4.30秒たったら反対側も同様におこなう
②マッケンジー体操
マッケンジー体操は、ニュージーランドの理学療法士が考案した、腰部のリハビリ法として知られています。
デスクワークの方など、猫背の姿勢になりがちな方におすすめのストレッチです。
・ポイント
無理のない範囲で気持ちよくおこないましょう。
仮に腰の痛みが強くなるようであれば直ちに中止し、専門家に相談しましょう。
・手順
1.ヨガマットや布団にうつ伏せで寝る
2.両ひじを付いた状態で上半身を起こす
3.可能であれば両手を付き、上半身を大きく反らす
4.30秒×5セットおこなう
③股関節のストレッチ
股関節が硬いと腰痛を起こしやすいのは、スポーツ界や医学界では定説となっています。
股関節を柔軟に保つと、腰にかかり負担を減らす効果が期待できます。
・ポイント
上半身を前に倒すとき、お辞儀しないように気を付けましょう。
上半身全体を前に傾けるイメージでおこなうのがポイントです。
・手順
1.椅子に腰かけ、左の足首を胡坐(あぐら)のように右ひざに乗せる
2.左手で左のひざ、右手で左の足首を押さえる
3.そのまま上半身をまっすぐ前へと倒す
4.30秒たったら反対側も同様におこなう
腰こり 解消方法
腰コリを解消する方法は、ストレッチだけではありません。
「ストレッチがなかなか続かない」
「身体が硬いのでストレッチが苦手」
といった方は、
- ツボ刺激
- 腰コリ解消グッズの利用
- 湿布
- 入浴
- ラジオ体操
といった方法も試してみましょう。
これらの方法で、腰コリの原因となる筋緊張を緩和する効果が期待できます。
また、血行を促進すると、身体の回復力を高める結果にもつながります。
それでは、それぞれのやり方について詳しく見ていきましょう。
腰こり ツボ
腰コリを解消するには、ツボを刺激するといった方法があります。
腰には先ほど紹介した志室を始め、腎兪(じんゆ)や大腸愈(だいちょうゆ)といった腰コリ解消のツボがあります。
ですが、ツボの正確な場所にこだわる必要はありません。
自分で押してみて気持ちいいと思う場所が、だいたいツボの位置だと思っていただいてOKです。
家族やパートナーがいる場合、手の親指や付け根、肘などで軽くツボを押してもらうとよいでしょう。
自分でツボを刺激するのであれば、テニスボールを布団に置き、その上で仰向けに寝るといった方法もあります。
ただし、強く刺激しすぎないよう気を付けてくださいね。
腰こり グッズ
腰コリを解消する場合、グッズを利用するといった手もあります。
腰こり解消グッズとしては、次のような商品が挙げられています。
ツボ押しまくら
腰コリを簡単に解消できる商品として、ツボ押しまくらが挙げられます。
名前はまくらですが、腰に使うタイプの商品もあります。
形や大きさはさまざまですが、ツボを押すための突起が付着しており、その上に寝そべる形で使用するのが一般的です。
ただし、やり過ぎるとかえって筋緊張が強くなるケースもあるため注意しましょう。
エレキバン
エレキバンには永久磁石が付けられており、ツボの場所に置くと、腰コリを解消する効果が期待できます。
また、エレキバンには身体の回復力を高める効果も期待されています。
地球全体にS極とN極があるように、人間の体内にも磁界があるのをご存じでしょうか。
体内にS極とN極があるため、神経伝達をおこなえるのです。
エレキバンを貼って体内の磁界バランスを整えると、身体の回復力を高める結果につながるとされています。
ストレッチポール
腰コリを解消するグッズとしては、最近人気のストレッチポールも挙げられます。
あおむけでストレッチポールの上に乗り、ユラユラと身体を動かすと、腰コリを気持ちよく解消する効果が期待できます。
一口にストレッチポールといっても、大きさや長さはさまざまです。
自分の身体のサイズにあったストレッチポールを選ぶようにしましょう。
腰こり 湿布
腰コリを解消する場合、湿布を利用するといった方法もあります。
湿布には消炎鎮痛剤が配合されており、コリや痛みを感じにくくさせる効果が期待できます。
湿布には大きく分けて冷感タイプと温感タイプの2種類がありますが、どちらを使っても効果に違いはありません。
冬場には温感タイプの湿布を使い、夏場には冷感タイプを利用するなど、使い分けるとよいでしょう。
入浴
腰コリを解消する簡単な方法の1つが、お風呂で身体を温めるやり方です。
お風呂で温まって血行がよくなると、腰の筋緊張を緩める効果が期待できます。
また、入浴によるリラクゼーション効果が、身体の回復力を高める結果にもつながります。
ただし、あまりにも熱いお湯につかると交感神経が優位になり、かえって血行不良を招きかねません。
38℃から40度程度のお湯に、ゆっくりと浸かるよう心がけましょう。
ラジオ体操
腰こりを解消するにはラジオ体操もおすすめです。
ラジオ体操は最近注目されるようになったダイナミックストレッチの一種です。
身体を動かしながらストレッチするため、効率よく筋肉を緩める効果が期待できます。
また、身体が硬い方であっても、ラジオ体操であれば簡単に取り組めるでしょう。
腰コリ解消だけでなく、リフレッシュ効果も期待できます。
毎朝の習慣にするのもよいでしょう。
まとめ
日本人の多くが腰痛に悩まされていますが、その前段階として腰のコリや張りが見られるケースも少なくありません。
いったん腰痛を発症すると、改善するまでに多くの時間とコストが必要となります。
今回の記事で、腰のコリや張りの段階で対処するのが重要だと、お分かりいただけたのではないでしょうか。
本文でもご紹介したストレッチやグッズで、早めに腰コリを解消してくださいね。